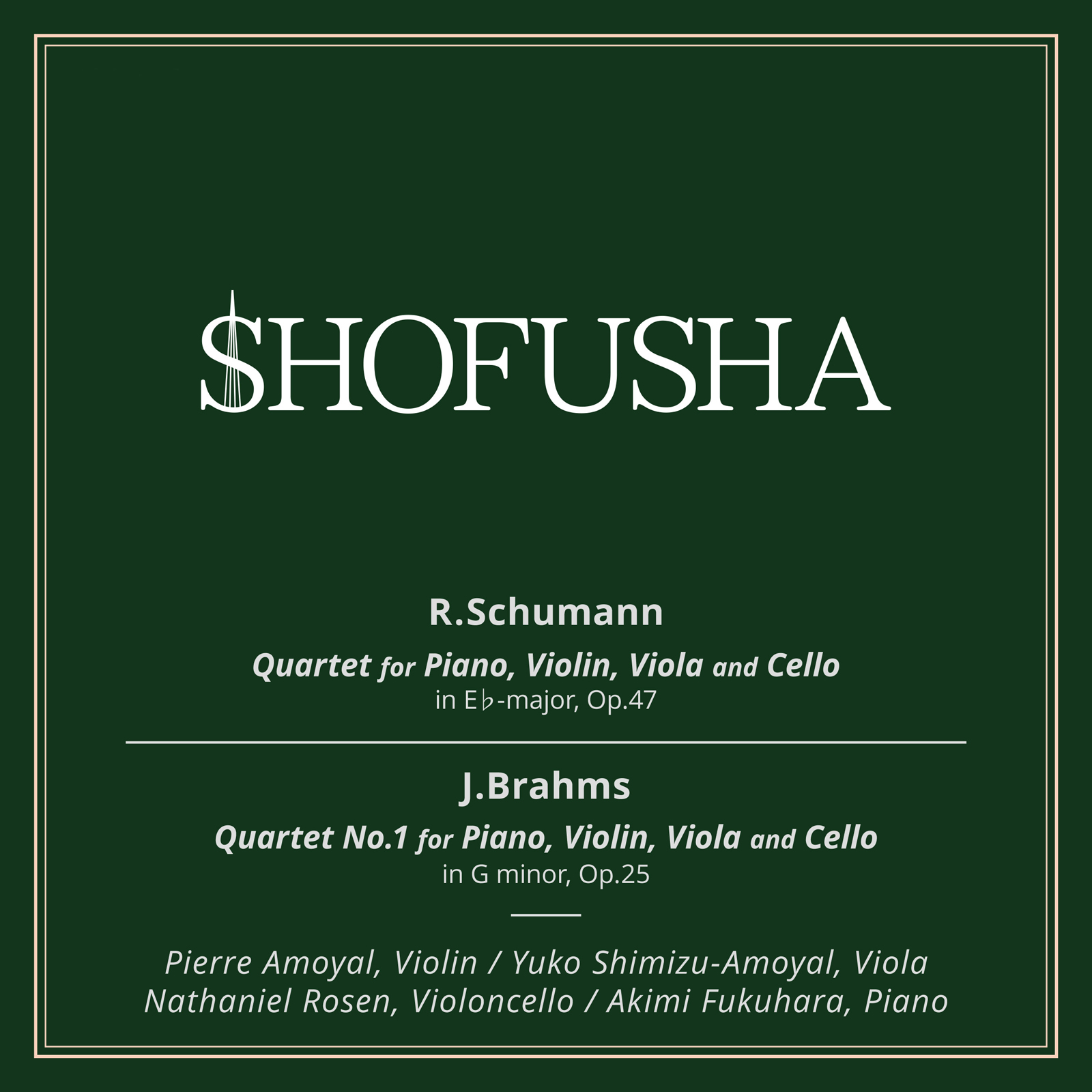【IIDA-0001】
R.シューマン:ピアノ四重奏曲 変ホ長調 作品47
J.ブラームス:ピアノ四重奏曲第1番 ト短調 作品25
- 曲目 :
- 【1】
Ⅰ Sostenuto assai-Allegro ma non troppo : 9’18”
【2】
Ⅱ Scherzo. Molto vivace : 3’32”
【3】
Ⅲ Andante cantabile : 6’42”
【4】
Ⅳ Finale. Vivace : 8’18”
- :
- 【5】
Ⅰ Allegro : 13’42”
【6】
Ⅱ Intermezzo : Allegro ma non troppo – Trio : Animato : 8’33”
【7】
Ⅲ Andante con moto : 9’03”
【8】
Ⅳ Rondo alla Zingarese : Presto : 8’47”
- アーティスト :
- ピエール・アモイヤル(ヴァイオリン YU IIDA 2013)
清水祐子(ヴィオラ YU IIDA 2014)
ナサニエル・ローゼン(チェロ YU IIDA 2017 )
福原彰美(ピアノ Bösendorfer)